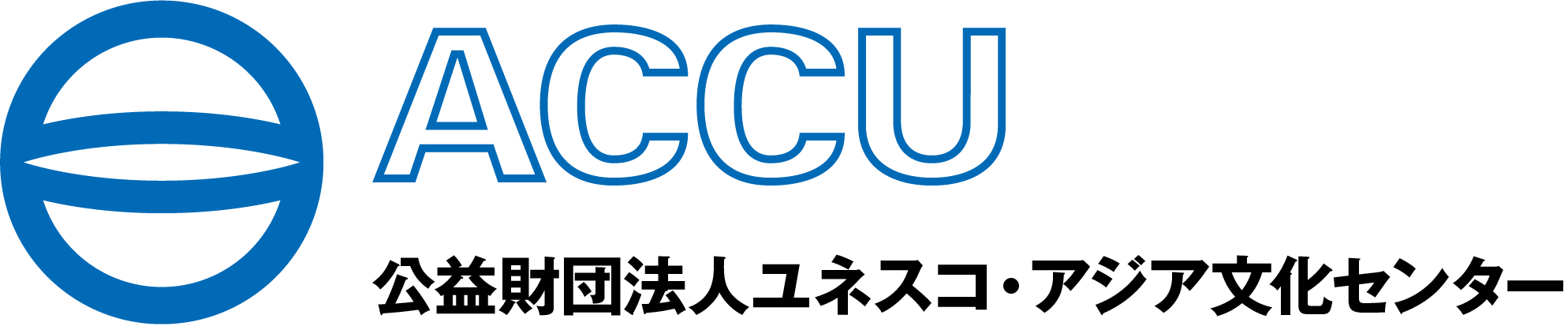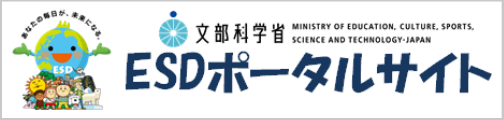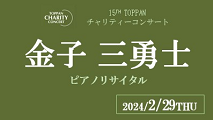NEWSお知らせ
ACCUからの最新のお知らせや活動情報などをお届けしています。
-
学習機会の拡充を目指した教育協力
ESD関連情報
SDGs関連情報
2024.01.09
『グローバル エデュケーション モニタリング レポート 2023 教育におけるテクノロジー』概要日本語版ローンチウェビナー -
教職員の国際交流
韓国との交流
中国との交流
タイとの交流
インドとの交流
2023.03.24
【教職員国際交流の冊子第3弾 発行のお知らせ】TREE of International Exchange -対話から未来をつむぐ -
SDGs関連情報
ユネスコ関連情報
2022.07.21
【募集開始】令和4(2022)年度ユネスコ未来共創プラットフォーム事業「海外展開を行う草の根のユネスコ活動(再委託)」の公募について(締切り:8月10日) -
ESDの実践を通した地域づくり
その他のESD推進事業
ESD関連情報
SDGs関連情報
2022.06.16
【「共に学び、地域をつくる ~実践者が描く協働の姿」「学びと協働による持続可能な地域づくり」発行のお知らせ】 -
教職員の国際交流
韓国との交流
中国との交流
タイとの交流
インドとの交流
2022.03.31
【教職員国際交流の手引き第2弾 発行のお知らせ】TREE of International Exchange -先生たちのための国際交流のとびら- -
学校教育におけるESD推進
ユネスコスクール支援
ESD関連情報
SDGs関連情報
2022.03.30
SDGs達成に向けたe-ラーニング教材(実践編)及び2021年度北陸ESD推進コンソーシアム成果報告書の公開 -
学習機会の拡充を目指した教育協力
SMILE Asia プロジェクト
ESD関連情報
2021.08.31
第13回トッパンチャリティコンサート『ことばのしらべ~produced by Masako Shindo』 -
ACCUからのお知らせ
SDGs関連情報
2021.06.21
ACCU設立50周年記念事業 Voice of Youth Empowerment 2021~地球の未来は、キミが変える~プレエントリー受付を開始しました! -
ACCUからのお知らせ
SDGs関連情報
2021.06.10
ACCU設立50周年記念事業「Voice of Youth Empowerment 2021~地球の未来は、キミが変える~」公式ホームページがオープンしました! -
学習機会の拡充を目指した教育協力
ESD関連情報
SDGs関連情報
2020.08.25
『グローバル エデュケーション モニタリング レポート 2020インクルージョンと教育』ローンチウェビナーのご案内
ACCUは、
多様な文化が尊重される
平和で持続可能な社会の
実現に貢献します。
PROGRAMME私たちの活動
ACCUはユネスコの基本理念に基づき、
アジア太平洋の人々と協働し、
誰もが平等に自らの意志で参加できる
学びの基盤づくりを促進します。
-
教職員の国際交流
国内外の教育関係者と出会い、海外に触れ、対話や交流を通じ、ともに学び合う機会を提供します。価値観を揺さぶり、未来を拓く、「先生」のための国際交流プログラムです。
-
青少年の国際交流
アジア太平洋地域の若者をつなぎ、ともに学び成長する機会を創出します。青少年を対象に、地球市民として平和で持続可能な世界の実現に向けて行動できる人材育成を目指しています。
-
高校生模擬国連
主体的に課題に取り組み、持続可能な社会を築き上げる次世代の人材育成プログラムです。国連会議のシミュレーションである模擬国連活動を通して、多角的・論理思考力や葛藤を克服する力を育てます。
-
学校教育におけるESD推進
ユネスコを主導機関として世界中で取り組まれている持続可能な開発のための教育(ESD)。ACCUでは国内外のネットワークを活用し、学校教育における平和で持続可能な未来の創り手を育む支援を行っています。
-
ESDの実践を通した地域づくり
ACCUは学校での持続可能な開発のための教育(ESD)の推進と共に、地域全体での持続可能な社会づくりを目指し、公民館などの社会教育施設や海外のコミュニティ学習施設との連携事業を進めています。
-
学習機会の拡充を目指した教育協力
全ての人が公平に教育を受けられる生涯学習社会の実現を目指します。国内外の様々な機関と連携して、草の根レベルのプロジェクトを実施したり、アドボカシー活動等を展開したりしています。
ACTIVITY REPORT活動レポート
ACCUは教育と文化の振興により
持続可能な社会の構築に貢献します。
FAVOR OF SUPPORT皆様のご支援で続く
未来があります。
FAVOR OF SUPPORT事業への
支援をしよう!
ACCUの事業は皆様からのご支援により成り立っています。
ユネスコの目指す平和な社会をアジア太平洋の多様な隣人と共に作って行くために、皆様のご支援をお待ちしています。
※ACCUへのご寄附は税制上の優遇措置を受けていただけます。
支援する